読者からのコメント
Shunjiさんからコメントをいただいた。それは、日本語の母音と英語の母音の関係という記事の中でいくつかいただいた。
今日の記事は、Shunjiさんのコメントについて言及しながら子音と母音の関係を考えてみたい。Shunji さんからは次のようなコメントをいただいている。
ta、sa等、子音に母音が続く時、母音を発声する時点で子音は消えます。しかし例えば/rάː//rˈɔː//rúː//jíː//júː/等は子音の音色を保ったまま母音を発声出来ます。これらの子音の音色を保ったまま歌が歌えますから。子音の音色を保ったままの母音を子音で止める個人のバリエーションもある。rob/rάb/ rule/rúːl等
「この子音の音色を保ったまま母音を発生できる」点に関して、私なりに考えてみたい。
半母音としての/r/
まず、子音/r/は半母音である。半母音とは性質は母音であるが持続することなく、対応する母音の構えからすぐに次の母音に移行する。それであるから、/r/の音を発声するときは、舌が口蓋の上に近づくが塞いだりはしない。塞がないで呼気が流れていくのであるから、母音的であると言える。しかし、塞ぎたくなるほど舌が上がるのであるから子音的であるとも言える。要は、母音と子音(摩擦音)の中間にある近接音(aproximant)なのである。
であるので、Shunjiさんの述べた「子音の音色を保ったまま母音を発声」するとは、半母音の持つ、「母音性に着目して、母音が連続している」ということを述べている、と解釈したい。
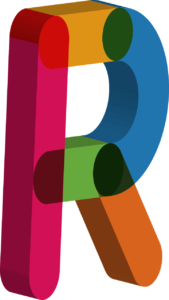
半母音としての/j/
/j/も半母音である。この音は前舌母音である/i/や/I/の付近から後続する母音の調音器官の位置に急速に移行する。要は、/j/には絶対的な舌の位置はなくて、続く母音よりも舌の位置が前寄りで高いという点が特徴である。/j/の位置は相対的に決められるということである。それゆえに、例えば、/jíː/を含む語である yeast /jíːst/を考えてみると、舌がかなり高い位置にあり、摩擦音を出すぐらいまでに近づくが、やはり触れないので母音的であるとも言える。それから/i:/の位置への舌が下がって後ろにゆく。これまた、「母音性に着目して、母音が連続している」と解釈できる。
/júː/は、/i/よりかなり後ろから出発して、/u:/よりは前に移動する。であるから、この場合は舌は口蓋に近づかないので非常に母音的である。ただ、普通の二重母音と比べると第1要素の/j/の発声の時間が短いので半母音であると考えられる。つまり、母音であるためには、ある程度の長さでの発声が可能であるべきだが、/j:/ではこの定義を満たしていない。
そのように考えると、Shunjiさんの述べた「子音の音色を保ったまま母音を発声」するというコメントは、/jíː//júː/にも当てはまるとも考えられる。
今回は、Shunjiさんのコメントに触発されて私の見解を述べたのである。







スッキリまとめていただいて良かったです。ありがとうございます。
>半母音とは性質は母音であるが持続することなく、対応する母音の構えからすぐに次の母音に移行する。
通常はやはりそうなんですね。意識的にするならば多くの母音にrの音色を混ぜることが出来ます。意識的でなくてもorder/ˈɔɚdɚ/。等の/ˈɔɚ/の/ɚ/はrの音色の入った/ɔ/ですし。⇒/ˈɔ+ɚ/。早い会話・個人のバリエーションにおいてa・e・i・o・uにrの音色が入っているか観察してみたいと思います。bruise/brúːz/rule/rúːl/等。
故G・馬場さんは英語が堪能だったらしいです。彼の英語の母音はほとんどr入りだったと推察されます。「あぁ そーですねー」/ɚ sɚ dɚ sɚ nɚ/と、それぞれの/ɚ/にaあ・oそ・eで・uす・eね・の音色をしっかり入れて言っていましたから。
*簡潔にお礼のコメントをと思ったのに長くなってしまいました。お礼を申し上げたく書きましたので最初の2行以外は本当に読まれたら削除していただきたく存じます。
Shunjiさんへ
最初の2行以降も貴重なコメントですので掲載したいと思います。「order/ˈɔɚdɚ/。等の/ˈɔɚ/の/ɚ/はrの音色の入った/ɔ/ですし。」これは、いわゆるr-coloringというアメリカ英語の特徴ですね。この音色とはよく耳にしますね。
G.馬場は英語が堪能であるというのは知りませんでした。ただ、彼は読書家で一般のイメージよりもはるかにインテリであるというのは聞いたことがあります。外国からの格闘家と対決することもあったので、自然と英語の必要性を感じたのかもしれませんね。