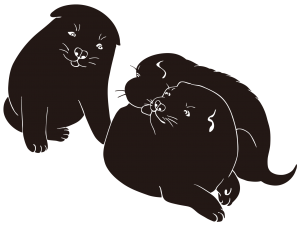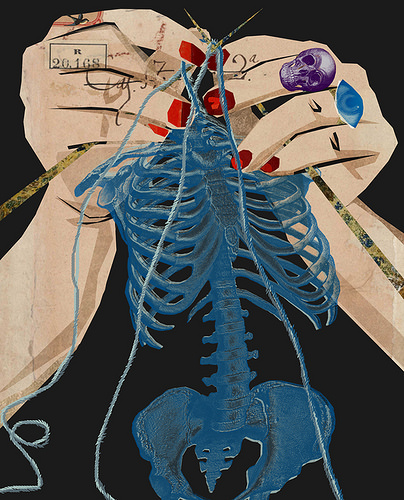○
最近はTwitter を読むことが多くなった。面白い話題がたくさん出てくるので読むのが楽しい。先日は、次のようなTweet を発見した。
Google翻訳を騙してやったぜ pic.twitter.com/h53KZK4kNB
— Akinori Ito (@akinori_ito) 2018年7月23日
これは面白い。Google 翻訳に猫という文字の中に一箇所だけ、狸という文字を入れたら、機械翻訳のくせに、それを見落として、Cat と翻訳したという話だ。
ところで、最近の機械翻訳の能力の向上は著しい。つい10年ぐらい前は、機械翻訳はまだまだだ。人間の手で修正しなければと言われたものだった。しかし、今では、抽象的な文章ならば、まだ問題はあるが、具体的な事柄ならば、かなり正確に訳すことができる。
日本語:私は自分の友人が東京駅で切符を買っているのを見つけました。
Googleの英語訳:I found my friend buying a ticket at Tokyo station.
このように正確な文を産出できる。もっとも、日本語の文をはっきりと翻訳しやすいように書く必要はある。それは、主語をきちんと書いて、述語がどれになるか、明確に示す必要がある。また長すぎる文はダメで、翻訳しやすいように、2、3の短文に分ける必要がある。
授業への影響として、和文英訳の作業ができにくくなったことが挙げられる。昔は、黒板に日本語を書いて、これを英語に訳しなさいという課題を与えることが可能だった。しかし、今では、生徒や学生はスマホの翻訳アプリに和文を入れると、すぐに英訳を入手するので、そんな課題の与え方は不可能になった。
近年は自由英作文が提唱されている。生徒や学生は、「自分が言いたいこと、表現したいことを自由に英文で綴れ」という風に教員から言われている。
最近は英作文という語の代わりに、ライティングという語がもっぱら使われる。これも時代の趨勢なのだろう。